一般性の高い独自の分子理論を開発し、それらを展開することで、 分子の関わる過程・化学現象の普遍的な理解の確立を目指している。
理論開発
一つ一つの分子は量子化学で理解できるが、無数の分子が集合すれば、集団としての性質が現れる。
自然には階層構造があり、総合的な視点が化学現象の理解にとって重 要である。
量子化学−統計力学融合理論
大部分の化学反応は 溶媒中で起こっており、こうした溶媒効果が反応の成否の重大な鍵を握っているいるにも拘わらず、 その理論は未開拓と言っても過言ではない。 本研究室で開発した分子性液体の積 分方程式理論と量子化学を融合した理論(RISM-SCF-SEDD法)は、 溶液内分子の化学過程の本質に迫る強力な方法である。この他にも大規模系の電子状態計算のための新手法など、 従来の電子状態理論の枠組みだけに捕らわれない、現実的な反応を解析できる新しい理論の開発とその応用を行っている。- 開発事例
- RISM-SCF-SEDD
- 3D-RISM-SCF
分子系の統計力学理論
化学は分子の集団を対象としており、統計力学の観点は重要である。 広く普及している分子シミュレーション(分子動力学法・モンテカルロ法)とは異なる観点から、 溶媒和構造や構造揺らぎを分子レベルで直接記述する新しい統計力学理論の開発を進めるとともに、 液体や生体内分子をはじめとする大規模系に対しての応用計算にも展開している。- 開発事例
- MC-MOZ
- Flexible-RISM
電子波動関数の理解
量子化学計算で得られる波動関数から様々な情報を引き出すための新しい解析法の開発を行っている。- 開発事例
- 第二量子化に基づく共鳴構造理論の定式化
- 電子波動関数に合致した双極子モーメント
現実の化学反応・化学過程への展開
現実の化学反応・化学過程は複雑である。
量子化学はもちろん統計力学や動力学などの周辺理論を総動員することで、第一原理に基づいた分子レベルの理解が可能となる。
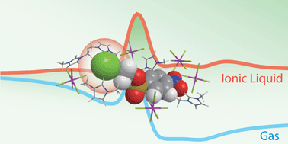 また、研究室で独自に開発した理論を駆使することで、
有機溶媒や水溶液などあらゆる種類の溶液内で起こる現象がターゲットとなる。
また、研究室で独自に開発した理論を駆使することで、
有機溶媒や水溶液などあらゆる種類の溶液内で起こる現象がターゲットとなる。
超臨界流体やイオン液体中の化学反応、pKaの計算など、世界で初めて第一原理的計算を実現した例も多い。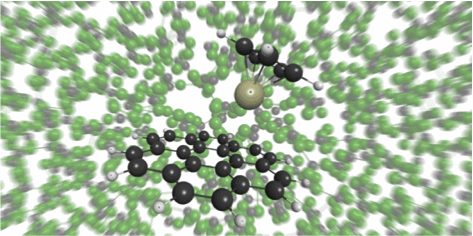
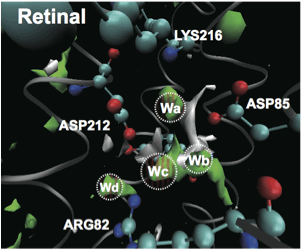 分子の統計力学理論に基づき、蛋白質内部の水和構造など分子レベルの情報を
導き出す。更に量子化学理論をはじめとする周辺理論と組み合わせることで、従来の方法では得られなかった
新たな視座の確立を目指している。
分子の統計力学理論に基づき、蛋白質内部の水和構造など分子レベルの情報を
導き出す。更に量子化学理論をはじめとする周辺理論と組み合わせることで、従来の方法では得られなかった
新たな視座の確立を目指している。
化学反応の理解
計算化学は反応の全貌を直接知る事のできる強力な手段であり、 既存の電子状態理論はもちろん、独自に開発した理論を駆使することで、溶液内の反応や触媒反応など 様々な化学反応の本質を明らかにしている。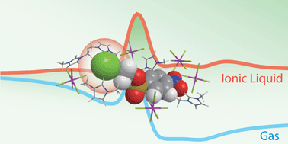 また、研究室で独自に開発した理論を駆使することで、
有機溶媒や水溶液などあらゆる種類の溶液内で起こる現象がターゲットとなる。
また、研究室で独自に開発した理論を駆使することで、
有機溶媒や水溶液などあらゆる種類の溶液内で起こる現象がターゲットとなる。超臨界流体やイオン液体中の化学反応、pKaの計算など、世界で初めて第一原理的計算を実現した例も多い。
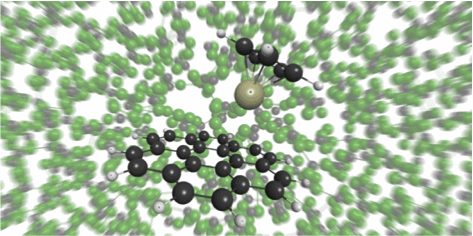
生体内分子系へのアプローチ
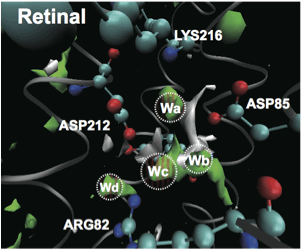 分子の統計力学理論に基づき、蛋白質内部の水和構造など分子レベルの情報を
導き出す。更に量子化学理論をはじめとする周辺理論と組み合わせることで、従来の方法では得られなかった
新たな視座の確立を目指している。
分子の統計力学理論に基づき、蛋白質内部の水和構造など分子レベルの情報を
導き出す。更に量子化学理論をはじめとする周辺理論と組み合わせることで、従来の方法では得られなかった
新たな視座の確立を目指している。